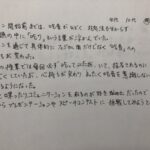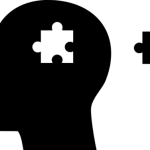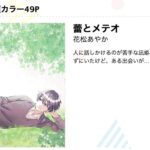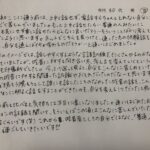話す時にどもりがあり、知的障害の可能性もある子の場合、どもりについての対応はどうすれば良いのでしょうか?この記事では、知的障害と吃音の関連について説明していきます。
もくじ
知的障害とは
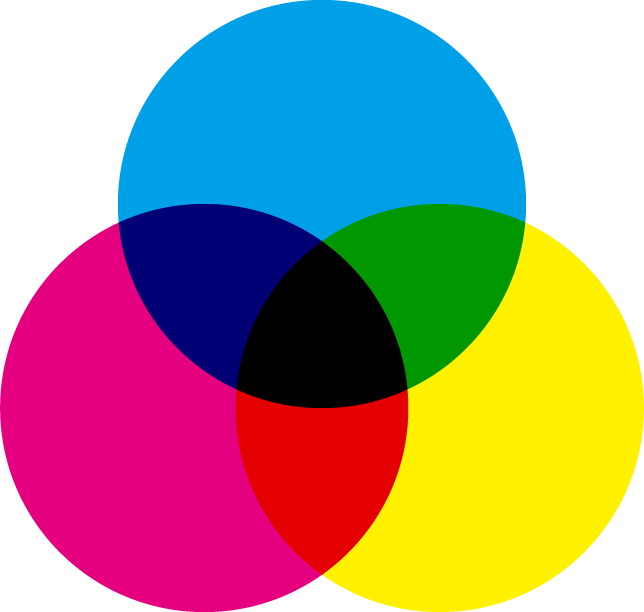
知的障害には、統一された定義というのはありませんが、世界保健機構が出している定義や、アメリカ精神医学会などが出している定義があります。
用語として、精神遅滞という言葉が使われることがありますが、精神遅滞と知的障害は、表現が違うだけで同じ意味です。
知的障害は、脳性マヒやてんかんなどの脳の障害と同時に起こったり、AD/HD(注意欠陥/多動性障害)や自閉症などの発達障害と合併して起こったりすることがあります。
判断基準には、以下の3つがあります。
・知的能力が低い
IQが70以下である。但し、以下の2つの基準を満たしていない場合は、IQが低くても知的障害ではないと考えられます。
・発達期に症状が現れている
18歳までに発症している
・適応能力の障害が2つ以上ある
意思伝達や自己管理など、社会生活に関わる様々な能力の障害がある
特徴
知的障害の特徴については、以下のようなことがあります。
・数量や時間の理解が苦手である
・ことばを覚えるのが苦手
・記憶をするのが苦手
・細かい作業が苦手
原因
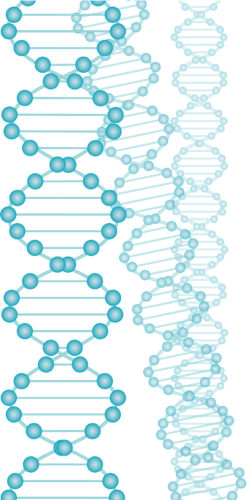
知的障害の原因は、生まれる前の原因が約8割といわれています。
出生前の原因として、遺伝子異常や染色体異常などの子供が生まれ持った原因と、母体の代謝異常や感染症など母体を通じて受ける影響によるものがあります。
出生後の原因には、頭部の外傷や養育環境、感染症などの原因があります。
吃音との関係性
吃音研究者バリー・ギターは、「吃音の原因として先天的な要因が関与する人がいるかもしれない。これらの要因には、出生児の身体的外傷、脳性麻痺、知的発達の遅れ、または情動的なストレス状況が含まれる」と述べています。
知的障害を持つ子の吃音発症率は、以下に示すように、ばらつきがあります。
知的障害(ダウン症を除く)の吃音発症の割合 最小0.8~最大20.3%
ダウン症候群の吃音発症の割合 最小2.5~最大45.0%
「特別支援教育における吃音・流暢性障害のある子どもの理解と支援」小林宏明・川合紀宗編著より引用
できること・周りの援助

本人と保護者のニーズに対して、専門家の指導・支援が受けることが大事です。そこで、障害と吃音への評価を行い、吃音改善への計画を立てていくことが必要です。場合に応じて言語訓練などを行っていくことが良いです。
まとめ
知的障害を持つ子が吃音を発症する確率は、知的障害を持たない子よりも高い傾向にあります。障害に合わせて、専門家の指導・支援を受けて改善計画を立てていくことが大事です。