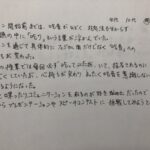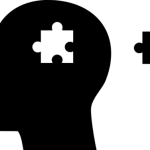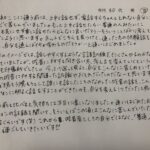この記事をお読みくださりありがとうございます。
私は東京都国分寺市で成人吃音の改善支援をしていまして、毎年この時期になると、吃音啓発の記事を書いています。
今日10月22日は国際吃音啓発の日です。
もくじ
吃音とは
吃音とは言葉がスムーズに話せない言語の障害です。
主な症状としては、言葉を連続して発したり、最初の第一音が出づらかったり、出だしの音を引き伸ばしたしります。
人によって症状の程度や発症時期も異なるため吃音の原因は完全にはわかっていないとされることが多いですが、子どもの頃からの吃音は体質的な要因があることを支持する研究者が多いです。
吃音は言葉の症状だけではなく、吃音が出ることへの不安・恐れ・恥ずかしさなど心理的な課題も同時に抱えている人が多いです。
「話す」といういわば多くの人が「当たり前のようにする行動」ができないことへのコンプレックスを感じている当事者は少なくありません。
吃音への誤解
吃音のない人から見ると、当事者は緊張したり焦っていて言葉が詰まっているように見えますが、実際には単なる緊張ではなく「吃音が出ることに対して緊張している」ことがよくあります。
人前で吃音が出ることを恐れ緊張し、さらに話しにくくなるという悪循環に陥るのです。
吃音のことを正しく知らない人から見たら、「もっと落ち着いて話せば良いのに」と思うかもしれませんが、症状が出てしまうために落ち着くことができず当事者は悩んでいます。
また、吃音の発症には親の育て方が関わっているとか、場数を踏めば治るなどとした根拠のない意見が未だに見られるため、まだまだ吃音を正しく理解していただく啓発を続ける必要があります。
文化を問わず世界の人口の1%はいると言われている吃音当事者は様々な誤解をされがちなのです。
当事者の意見
それでも近年では吃音の自助団体などの様々な活動を通じてメディアなどでも吃音が取り上げられることが増えてきてはいます。
正しい吃音の知識が知られることはとても良いことではないかと思いますが、一方で、当事者が吃音への多様な価値観があることも浮き彫りになってきています。
少し前に某民間吃音団体がバラエティ番組に苦情を入れたことがありましたが、その際にも当事者の方々からは賛否様々な意見が寄せられました。
吃音があるからと言って、全ての人が吃音に対して同じ考えを持っているわけではありませんし、「他人から吃音に対する捉え方を一方的に決めつけられるのは嫌だ」と言う人も多いです。
吃音があることを知ってもらいたい人もいれば、あまり触れないでもらいたい人もいるのです。
当事者の現状の差異
そもそも吃音は個人による症状の違いもあれば、周りの人が理解されていて吃音があっても支障なく生活ができている人もおり、現状は人によって異なります。
吃音があっても職に困らない人(専門職など職業によっては吃音がそこまで支障にならない仕事もあります)もいますし、日々吃音の不安を抱えながらなんとか仕事に従事している人もいます。
吃音のことを理解してもらえずに孤立してしまっている人の中には、吃音のある人と繋がりたい人、繋がりたくない人もいます。
このように、当事者によって吃音の捉え方は多様です。
当事者の間でも様々な意見があることを踏まえると、吃音のない人からしたらどのように接することが正解かわからないという意見があるのも当然かもしれません。
吃音のある人を取り巻く環境の課題
当事者にとって、吃音を理解してくれる方がいることはとても有難い存在です。周囲に理解され、「どもっても大丈夫なんだ」と思えることで生活は楽になります。
吃音のことを知らない人に全てを理解してもらうことは難しいですが、吃音があってもお互いを尊重できるような関係が多いほど当事者は楽に過ごせます。
ただ、吃音を取り巻く環境においては、周囲に吃音を伝えたとしても本人の望むような形で周囲が対応してくれるかというと必ずしもそうでもありません。
英検などでは吃音があることを申請することによって配慮を受けられるとありますが、実際には申請したからと言って楽に話せるわけでもなく配慮を受けたと感じない人もいます。
学校では、先生に吃音のことを伝えても先生がどう対応して良いかわからずに本人は不安を抱えたままということも起こりえます。
このように吃音がある人に対する環境課題はまだまだあります。
一人ひとりのあり方が尊重される社会へ
しかし、吃音がある人たちは、当たり前ですが吃音がない人と同じく自分の人生を一生懸命に生きています。
自分の能力を最大限に発揮して生きていくためには、周囲への認知だけではなく一人ひとりが吃音を抱えながらもどう自分らしく人生の歩みを進め、その生き方が尊重されていくかが大事になってきます。
全ての個人的な課題に共通することかもしれませんが、単に吃音をわかってくださいと伝える時代から、1人をより尊重することが大事な時代になっていくと思います。
今後も益々吃音を持つ一人ひとりの方が、自分の置かれた環境で自身の力を最大限に発揮され、周囲に理解されることを願っています。
東京吃音改善研究所代表
畦地泰夫